〜行政書士の視点と、他士業との連携の大切さ〜
「資金繰り表を作ったことはありますか?」
創業相談の現場でこの質問をすると、多くの方が「まだ手を付けていない」と答えます。新規開業・スタートアップ支援資金や小規模事業者持続化補助金の申請には熱心でも、日々の資金の出入りを把握する資料作りは後回しになりがち。
しかし、資金繰り表を軽視すると「黒字倒産」という最悪の事態を招きかねません。飲食店や雑貨店など、開業後すぐに資金が動く業種ほど、この”現金の流れ”を見える化することが命綱になります。
業際の明確化と行政書士の立ち位置
| 専門家 | 資金繰り表への関わり方 |
|---|---|
| 税理士 | 帳簿付、決算、税務申告専門 「数字の正確性」を担保 |
| 中小企業診断士 | 経営分析、改善提案、戦略的な数字の読み解き |
| 行政書士 | 制度活用の観点から書類の説得力を評価・補強 |
行政書士は会計処理や税務相談に踏み込むことはできません。ただし、創業計画や補助金申請において必要となる「資金繰り表の原案」について、依頼者からヒアリングした内容をもとに整理することは可能です。
数字面の詳細検討や税務判断が必要になれば、信頼できる税理士や中小企業診断士をご紹介するなど、適切な専門家につなぐのも行政書士の役割です。
資金繰り表が「ない」ことで起こる問題例
1. 希望的観測による売上設定
例:開業希望地域での飲食店開業
- 楽観的予想:「都市部に近いから1日50人は来る」
- 現実:立地認知に6ヶ月、実際は1日15人程度だったというようなケース
2. 固定費の過小評価
見落としがちな開業エリアの実情:※福岡県内を想定とした例
- 夏場のエアコン代(九州の猛暑で電気代が2倍に増加)
- 台風・大雨時の売上減少
- 従業員確保競争による人件費上昇
3. 補助金入金タイムラグの軽視
持続化補助金の実際:
- 採択から入金まで約9〜10ヶ月
- その間の運転資金確保が未計画
4. 制度活用の機会損失
- 追加融資のタイミングを逃す
- マル経融資(商工会議所または商工会での一定期間の経営指導必要)の活用を見逃す
資金繰り表を作るメリット
- 補助金・融資の申請に説得力が増す 創業計画書や補助金申請書に資金繰り表を添付できれば、審査官や金融機関に「数字の裏付けがある」と伝わります。行政書士は、この“書類の完成度を高める”観点から資金繰り表を推奨します。
- 制度のタイムラグを意識できる 補助金は採択後すぐに振り込まれるわけではありません。入金までに数か月のズレが生じます。行政書士としては「この補助金を使う場合、入金は〇月以降になるので、その間の資金をどう確保しますか?」と確認し、他士業につなげます。
- 最悪シナリオを制度面から検証できる 資金ショートが起きた場合、追加融資や保証制度をどう活用できるか。ここは行政書士の制度知識が活きる場面です。数字そのものの分析は税理士・診断士に委ねつつ、制度との接続点を示せます。
行政書士だからこそ提供できる価値
制度面からの「書類補強」視点
行政書士は、会計処理や税務判断の専門家ではありません。しかし、補助金や融資といった「制度を通す書類」を作成する上では、資金繰り表をどう申請書類に結びつけるかという視点が欠かせません。制度をよく知る立場だからこそ、行政書士は次のような価値を提供できます。
⭕ 行政書士ができること
1. 書類審査での評価ポイントの指摘
補助金や融資の審査では、「数字の根拠が示されているか」が厳しくチェックされます。
たとえば「月100万円売れる予定です」とだけ書かれていると、根拠のない希望的観測と見なされます。そこで行政書士は、売上根拠を「週末来店30名 × 客単価1,500円」「平日来店20名 × 客単価800円」といった形で整理し、数字にストーリーを持たせるサポートが可能です。こうした“表現の工夫”は、審査官に伝わるかどうかを大きく左右します。
2. 制度のタイムラグ情報の提供
補助金や融資制度には「申請から入金・実行までの時間差」が必ず存在します。このタイムラグを把握せずに計画すると、資金ショートに直結します。
行政書士は制度の特徴を熟知しており、たとえば:
- 持続化補助金:採択後、実績報告や審査を経て入金されるまで約9〜10ヶ月かかることが多い
- スタートアップ支援資金:申請から融資実行まで1〜2ヶ月の期間が必要
- マル経融資:経営指導を6ヶ月以上受けた後で審査に入り、さらに1ヶ月程度かかる
こうした情報を事前に共有することで、事業者は「資金が入るまでの期間をどうつなぐか」を具体的に考えられます。
3. 最適な専門家への橋渡し
資金繰り表の原案を行政書士が整理することはできますが、詳細な会計処理や税務相談、経営改善提案が必要になる場面も少なくありません。そうしたときには、税理士や中小企業診断士にスムーズにつなげる役割を担います。
事業者にとっては「誰に相談すればいいか分からない」こと自体が大きな不安要素です。行政書士が窓口となって適切な専門家に橋渡しすることで、余計な遠回りを防ぎ、より安心して事業を進めることができます。
行政書士がサポートする3つの効果
1. 申請書類の説得力向上
- Before:「別の店は月100万円くらい売れるらしい」
- After:「週末単価1,500円 × 平日単価800円で月98万円、根拠は近隣競合店舗の平均客単価データ」
こうした整理を経て提出された申請書類は、“説得力のある事業計画”として評価されやすくなります。実際の計画書では更に細分化した情報を元に具体的かつ説得力のある書類を作成していきます。
2. 制度タイムラグの事前把握
制度ごとの時間差を踏まえて、「補助金入金は9ヶ月先なので、それまでの運転資金をどう確保するか」「マル経融資は申請できるのは来年以降になるから、それまでの資金繰りをどうするか」といった、現実的な時間軸での計画立案をサポートします。
3. 最悪シナリオへの制度的対応
事業は常に順調とは限りません。もし資金ショートが見込まれる場合には:
- セーフティネット保証制度の利用
- 追加融資の申込み手順の整理
- 緊急時に活用できる補助金制度の確認
など、制度面からのリスク回避策を提示できます。数字の詳細分析は税理士・診断士に委ねつつも、「制度をどう使ってリスクに備えるか」は行政書士だからこそ示せる視点です。
久留米・福岡エリアでの実践例
地域特性を活かした他士業連携
久留米商工会議所との連携例:
- 行政書士:マル経融資申請書類の準備支援
- 商工会議所:6ヶ月間の経営指導
- 連携税理士:指導期間中の資金繰り表作成
- 行政書士:融資面談での資料説明サポート
結果:計画的な資金管理で開業後の資金ショートを回避
他士業との違いと連携のポイント
- 税理士:日々の帳簿付け、決算、税務申告を専門とする。→ 資金繰り表の「数字の正確性」を担保する役割。
- 中小企業診断士:経営分析、改善提案、事業戦略を専門とする。→ 資金繰り表を用いた「経営改善の方向性」を示す役割。
- 行政書士:許認可・補助金・融資など“制度を通す書類作成”が専門。→ 資金繰り表を「書類に説得力を与える補助資料」として扱い、制度活用の橋渡しを担う。
行政書士ができるのは「数字を整えること」ではなく、「数字が制度を通すために足りているかどうか」を確認すること。そして不足があれば、税理士や診断士に連携することです。
まとめ:資金繰り表は「制度を活かすための必須アイテム」
開業準備において、つい目に見える部分——店舗デザインやSNS戦略——に目を奪われがちです。しかし、制度を活用して事業を安定させるためには、数字の裏付けが不可欠です。
資金繰り表は事業計画書の一部として位置付けられるものであり、行政書士が依頼者からのヒアリングを通じて整理し、申請書類に反映させることが可能です。数字面の細かな分析や税務上の判断が必要な場合には、必要に応じて税理士や診断士と連携すればより確実ですが、まず入口の段階で資金繰り表を形にして制度活用につなげることこそ、行政書士が得意とするサポート領域です。
補助金・融資・許認可の申請を確実に通すために。
そして、事業者が安心して事業を続けられるために。
資金繰り表は「倒産防止のワクチン」であり、行政書士は制度面からの視点を活かし、必要に応じて他士業とも連携しながら、最も効果的に活かす伴走者なのです。
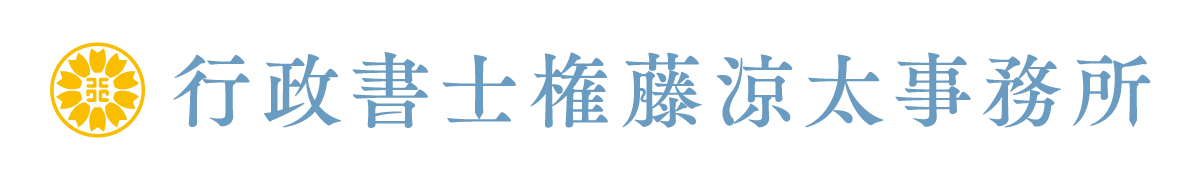










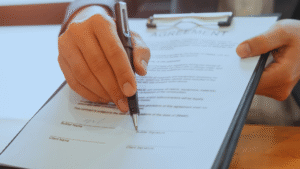
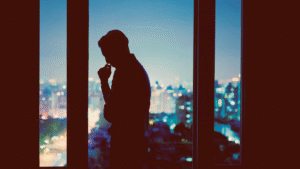
コメント