行政書士として、そして猫と暮らす者として伝えたいこと
はじめに
私自身も猫たちと暮らしています。長い子はもう15年以上、日々の出来事を共にしながら歩んできました。そばにいてくれるだけで、日常に安心と温かさを与えてくれる存在です。もはや「ペット」という言葉では足りず、かけがえのない家族の一員です。
しかし、法律上ペットは「物」として扱われる存在であり、人間のように相続人になることはできません。ここに大きなギャップがあり、「万が一の時、この子はどうなるのだろう」という不安を抱える飼い主が増えています。行政書士として相談を受ける中でも、この「ペット法務」に関する関心は年々高まっていると実感します。
福岡県そして久留米でも「ペット相続」や「ペット信託」に関する相談は少しずつ増えている現状です。今回はその基本と、行政書士がお手伝いできることをまとめます。
ペット相続に関するよくある相談
- 「もし自分に何かあったら、この子を誰に託せばいいの?」
- 「うちの犬に財産を残したい。そんなことはできるの?」
- 「兄弟が相続で揉めて、猫の行き先が決まらないのではと心配」
- 「一人暮らしなので、老後にペットを残してしまうのが怖い」
どれも切実で、飼い主の愛情と責任感が伝わってきます。ですが、現行法ではペットは相続人ではなく「相続財産の一部」とされ、そのままでは”誰かの所有物”として扱われてしまうのです。
ペットに財産を残せない理由と代替策
1. 法律上ペットは「物」
民法上、相続できるのは「人」に限られます。残念ながらペットは相続人になれず、直接「財産を残す」ことはできません。
2. 代替策として可能な方法
遺言書で特定の人にペットを託す
「長女に愛猫ミケを託す」と明記することで、法的な意思表示になります。
- 期間目安:約2~4週間
- 費用目安:遺言書作成支援 約5万円~
※費用は遺言の方式や内容によって変動します。例えば、
- 自筆証書遺言:比較的シンプルに作成でき、支援費用は約5万円程度から。
- 公正証書遺言:公証人との打合せや証人手配が必要になるため、行政書士報酬も8万〜15万円程度が一般的。さらに、公証人手数料(財産額によって2〜5万円程度)が別途必要です。
- 財産の種類(不動産・預貯金・動産など)が多岐にわたる場合や、相続人間の調整が必要な場合には追加費用が発生することがあります。
負担付遺贈
「ペットを飼うことを条件に財産を遺す」という形です。
例えば「愛犬の世話を続けることを条件に○○万円を長女に遺贈する」といった遺言内容になります。
一見シンプルですが、この仕組みにはいくつかのメリットと注意点があります。
メリット
- 飼育を条件化できる安心感 単に「ペットを長女に託す」と書くだけでは、後になって「実際に飼育するかどうか」は本人次第になります。 しかし負担付遺贈にすれば、「財産を受け取る代わりに飼育を継続する」という義務が生じるため、ペットの生活を守る確実性が高まります。
- 財産で飼育費をカバーできる ペットの寿命は10年以上に及ぶこともあります。特に犬や猫は医療費もかかるため、「飼育を引き受けた人の負担が大きい」という不安があります。 負担付遺贈では「飼育と引き換えに財産を渡す」ので、金銭的負担の軽減になり、引き受ける側も安心して同意しやすくなります。
- 現実的な制度で利用しやすい ペット信託のように大掛かりな契約や銀行との調整を必要とせず、遺言書に明記することで利用可能。実務でも取り入れやすい仕組みです。
注意点
- 受遺者が拒否する可能性 財産を受け取る代わりにペットの飼育義務を負うことになるため、受遺者(例:長女)が「ペットを飼えない」と断る場合もあります。その場合、遺言で指定した内容が実現できなくなる可能性があります。
- 飼育状況を監督する人が必要 「飼っている」と形式的に見せかけるだけで、実際には世話が不十分になるリスクもあります。そこで「遺言執行者」や「第三者監督人」を指定しておくと、遺言内容の実行を確実にチェックできます。
- 財産額の設定に配慮が必要 少なすぎれば飼育に支障が出ますし、多すぎると他の相続人から不満が出ることもあります。たとえば「毎月の飼育費×平均余命年数」を基準に計算するなど、合理的な算定が望まれます。
ペット信託
ペット信託とは、飼い主(委託者)が信頼できる人や団体(受託者)と契約を結び、自分の財産を「信託財産」として預け、その財産をペットの飼育費に充ててもらう仕組みです。
例えば、飼い主が亡くなった後に「信託契約に従って、毎月○万円を給付してペットの飼育に使う」といった形で運用されます。委託者・受託者・ペットの世話を実際に行う人(飼育者)を別に設定できるのも特徴です。
利用の流れ(典型例)
- 飼い主(委託者)が信託契約を結ぶ
- 受託者(信頼できる親族や専門機関)が財産を管理
- 指定された飼育者に毎月の生活費や医療費を給付
- ペットが亡くなった時点で信託契約を終了し、残余財産を相続人へ戻す
メリット
- 長期的な飼育保証が可能:遺言と違い、生前から契約が効力を持つため「認知症になった場合」などにも対応できる。
- 財産の使い道を限定できる:渡したお金が必ずペットのために使われるよう管理できる。
- 柔軟な設計:受託者と飼育者を分けたり、監督人を置いて運用状況をチェックさせることも可能。
課題
- 歴史が浅い:日本でペット信託が登場したのは2013年で、事例がまだ少なく制度的な知見が十分ではない。
- 受託者確保の難しさ:信頼できる親族がいない場合、受託者探しが難航する。法人受託も限られている。
- 金融機関の対応:信託専用口座を受け付ける銀行が限られており、現実的な運用に制約がある。
- 費用負担の大きさ:初期費用(契約作成・信託設定)に加え、受託者報酬・銀行手数料などが必要。少額の財産だと現実的に運用しづらいケースもある。
期間・費用目安
- 期間目安:約2~6ヶ月(契約設計・受託者調整を含む)
- 行政書士報酬:10万円~20万円(契約設計サポート部分)
- 別途必要な費用:信託財産として拠出する金額(50万~100万円以上が多い)、受託者報酬、銀行口座維持費など
⚠️ペット信託の制度運用は実務経験のある専門家・金融機関によって大きく対応が異なります。契約前には必ず専門家への確認が必要です。
行政書士にできること
遺言書文案の作成支援
ペットの飼育先や条件を明記する遺言を作成し、法務局での保管制度を利用する手続きも支援できます。
負担付遺贈や飼養委託契約の提案
飼育を条件に財産を残す文言を盛り込む、あるいは生前に「飼養委託契約」を交わしておくことで安心が増します。
関係者との合意書作成
相続人同士で「ペットの飼育を誰が担うか」を事前に文書化しておくと、争いを未然に防げます。
必要に応じた専門家連携
ペット信託や税務面の検討が必要な場合は、信託会社や税理士に橋渡しを行い、全体の体制を整えます。
費用と期間の目安
| 手続き内容 | 期間 | 行政書士報酬目安 | 別途必要な費用(実費等) |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言支援 | 2~3週間 | 5万円~10万円 | 法務局保管の場合、手数料 3,900円 |
| 公正証書遺言支援 | 3~4週間 | 8万円~15万円 | 公証人手数料 約2~5万円(財産額による) |
| 負担付遺贈契約書作成 | 2~3週間 | 7万円~12万円 | 印紙代・相手方の費用負担が発生する場合あり |
| ペット信託設計サポート | 2~6ヶ月 | 10万円~20万円 | 信託財産(50万円~100万円以上)、受託者報酬、銀行手数料等 |
※上記は行政書士業務全体の一般的な参考価格です。実際のご依頼内容や状況により変動いたします。当事務所にご依頼いただく場合は、個別の事情をヒアリングのうえで正式なお見積りをご提示いたします。
※ペット信託の場合は、信託財産や受託者報酬など別途必要な資金が大きくなります。行政書士は信託契約の設計・書類サポートを中心に対応します。
行政書士として、飼い主として思うこと
猫と暮らす私自身、「もし自分がいなくなったら、この子たちはどうなるのだろう」と考えずにはいられません。自分だけでなく、共に暮らす家族や日常的に世話をしてくれる人がいなくなったとき、行き先はどうなるのか。
遺言や契約書は「堅苦しいもの」と思われがちですが、残された大切な家族(=ペット)を守るための”愛情の証”だと感じています。
特に単身者や高齢者の飼い主からは、「周りに迷惑をかけたくない」「最後まで責任を果たしたい」という声が多く聞かれます。行政書士は、その思いを具体的な書類に落とし込むことで安心を形にするお手伝いができます。
まとめ
- ペットは家族同然ですが、法律上は「物」として扱われる
- だからこそ、飼い主の意思を遺言や契約で明確に残すことが重要
- 行政書士は遺言作成や契約書の支援を通じて、ペットの未来を守る仕組みを整えられる
- 負担付遺贈は「現実的かつ利用しやすい方法」として有効だが、監督人や財産額の設定に工夫が必要
- ペット信託はより確実だが費用・期間の負担が大きいため、適切な制度選択が大切
ペットと共に暮らす幸せは何ものにも代えがたいものです。だからこそ「もしも」に備えて法的な準備をしておくことが、愛情ある飼い主としての最後の責任だと思います。
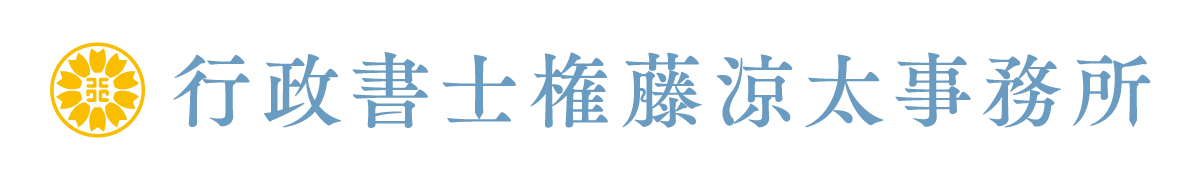




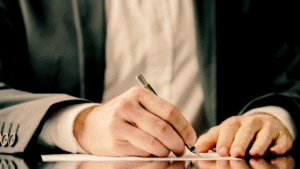
コメント