「ヨーロッパの蚤の市で買ったアンティーク雑貨。これ、日本でそのまま売っても大丈夫?」
そんな風に思ったことありませんか?
ここ数年、海外の蚤の市やヴィンテージショップでアンティーク雑貨を買い付けて、日本でネット販売したいという相談が増えています。 Instagramやネットショップでもこうした販売ケースを見かけることが増えましたよね。
そこで確認しておきたい許認可申請のひとつが“古物商許可”です。
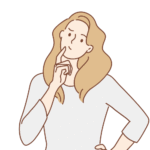
仕入れたものが中古品だったら、許可が必要?
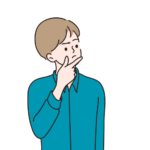
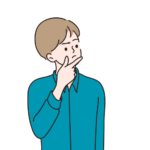
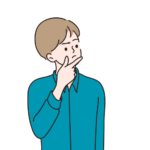
海外旅行で買ってきた雑貨なら問題ない?
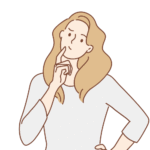
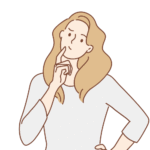
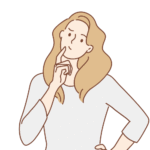
自宅でネット販売だけしてても許可はいらない?
今回は、そんな「古物商許可って何?」という疑問を持っている方のために、 行政書士の立場からできるだけわかりやすく、かみ砕いて解説していきます。
【古物商許可とは?】
古物営業法 第3条(許可) 第三条 古物営業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
つまり、「古物営業」(=古物の売買・交換・委託販売などを事業として行うこと)を行うには、その営業所ごとに許可を取る必要があるというルールです。 実際に申請する際は、営業所の管轄となる警察署(生活安全課など)に提出する形になります。
古物営業法 第2条(定義) 第二条 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 一 古物を売買し、又は交換する営業(以下「古物商」という。) 二 古物の売買又は交換の委託を受ける営業(以下「古物市場主」という。) 三 古物を買い、又は交換し、その物品を貸し付ける営業 そして、「古物」とは以下のように定義されています: 同条第二項 この法律において「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品であっても一度使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物商許可とは、古物営業法という法律に基づき、中古品などを売買・交換する事業を行う際に必要となる許可です。 この許可は、営業所のある都道府県公安委員会(≒警察)から取得する必要があります。
ここでいう“古物”とは、「一度使用された物品」または「未使用であっても使用のために取引された物品」のこと。 簡単に言えば、「一度誰かの手に渡った物」と考えるとわかりやすいでしょう。
例えば:
- 中古の家具や衣類、ブランド品、古本、カメラなど
- アンティーク雑貨やリサイクル品
- 新品に見えても“買取品”として仕入れた物
などは、すべて「古物」に該当する可能性があります。
【許可が必要なケース/不要なケース】
「じゃあ、どんなときに許可が必要なの?」 ここは特に気になるポイントだと思います。
<古物商許可が必要なケース>
- 中古品を継続的に仕入れて販売する場合
- 国内の業者や個人から中古品を買って販売する
- ネットショップ・フリマアプリなどを通じて反復継続して販売する
- 自分で修理・リメイクして中古品を販売する場合も原則必要
- 実店舗型のリサイクルショップを開業する場合
- 古本屋を運営し、中古書籍を仕入れて販売する場合
- 中古のゲーム・CD・DVDなどを取り扱う場合
- 中古家電・スマートフォン等の買取販売業を行う場合
- 中古車や自転車など、動産の販売を業として行う場合
<古物商許可が不要なケース>
- 自宅にある不用品を一時的に売る
- 海外で自分自身が直接買い付けた中古品を販売する(※大阪府警HPで「不要」と明示。下記に引用元掲載)
- ハンドメイド作品など、自作した物の販売
- 古物を仕入れずに、新品のみを扱う
※ただし、販売の規模や営利性によっては、最初は不要でも後から「営業」とみなされる可能性もあるため慎重に判断を。
【海外仕入れの雑貨は古物商許可が必要?】
ここがまさに悩みどころ。
結論として、「海外で自分自身が直接買い付けた中古品を、日本でそのまま販売するだけであれば、古物商許可は不要」とする見解が一部都道府県(例:大阪府警HPなど)で明示されています。
外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3685.html 大阪府警HPより引用
ただし、これはあくまで仕入れルートや販売形態が限定されたケースに限られます。 実際には、以下の点を必ず事前に確認する必要があります。
【販売前に確認すべきこと】
- 販売経路(実店舗・ネット販売・イベント出店など)
- 商品の仕入れ元(海外の個人か業者か、輸入業者を介したものか)
- 販売の継続性や営利性(趣味の延長か、事業として行うか)
- 営業所の所在地を管轄する警察署の判断
※ご注意ください:古物商許可の運用は都道府県ごとに若干の差があるため、「自分の場合は許可が必要かどうか」については、必ず営業所の所在地を管轄する警察署に直接問い合わせてください。特にネット販売など、複数の販路を持つ方は、販売方法を含めて明確に説明したうえで、判断を仰ぐことが大切です。
また、海外からの仕入れに関しては、古物商許可とは別に「関税の課税」「食品衛生法や動物検疫・植物検疫」など、輸入に関わる各種法規制が関係する場合があります。特に雑貨の中に食品や革製品、木製品などが含まれる場合は注意が必要です。 そのため、輸入ビジネスとしての全体像を把握し、関係省庁や税関への確認もあわせて行うことをおすすめします。
【申請の流れと必要書類】
古物商許可を取得するには、営業所所在地を管轄する警察署に申請書類を提出します。 申請後、標準処理期間として約40日程度が見込まれます(都道府県によって異なる)。
主な必要書類(個人申請の場合)
- 古物商許可申請書(各都道府県様式)
- 住民票(本籍記載あり)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 略歴書(過去5年分)
- 誓約書
- 営業所の賃貸契約書や使用承諾書
法人の場合は、これに加えて登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や定款の写しなどが必要です。
なお、古物商許可は一度取得すれば、更新制度はなく基本的に有効期間の定めはありません(※届出義務など一部変更時対応は必要)。 そのため、将来的に販路拡大やネット販売などを検討している方にとっては、早めに取得しておくことで後の手続きをスムーズに行えるというメリットもあります。
【ネット販売でも対象になるの?】
はい、対象になります。
インターネットでの販売は「媒体が違うだけ」で、古物営業法上の“営業行為”と見なされます。 フリマアプリ・ネットショップ・SNS・ECモール(BASE、STORESなど)もすべて含まれます。
つまり、店舗を持たない“無店舗型営業”であっても、反復継続して中古品を販売していれば許可が必要になる可能性が高いのです。
特に、古物営業法違反は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則があるため、無許可営業はリスクが大きいです。
【行政書士に依頼するメリット】
申請自体はご本人でも可能です。 しかし、以下のような理由で行政書士への依頼が選ばれています。
- 何が必要か自分では調べきれない
- 警察署とのやり取りが不安
- 書類の記載ミスで再提出になるのを避けたい
- 賃貸契約の条件が微妙で、使えるか確認したい
- 他の開業準備などで時間が足りない、手が回らないなど効率を図りたい時
行政書士は、各都道府県のローカルルールも踏まえて、申請を正確・スムーズにサポートします。
【まとめ】
古物商許可は、「営業するつもりがない」つもりでも、実際には法的に“古物営業”とみなされるケースがあるため注意が必要です。 特にネット販売や海外仕入れが絡む場合には、判断が難しい部分も多いため、自己判断せずに事前確認を徹底しましょう。
そして実は、古物商許可って一度取得すれば更新もなく、有効期間の制限もありません。 将来的に販路を増やしたり、ネット販売や委託販売などに展開していく場合にも、先に取得しておくことで「やりたいときにすぐ動ける」体制が整います。
「取っておいて損はない」どころか、「思ったよりメリットが大きい!」というのが、古物商許可です。
難しそうに見えても、ポイントを押さえれば決して難解な手続きではありません。 一歩踏み出して、安心して販売できる体制を整えていきましょう。
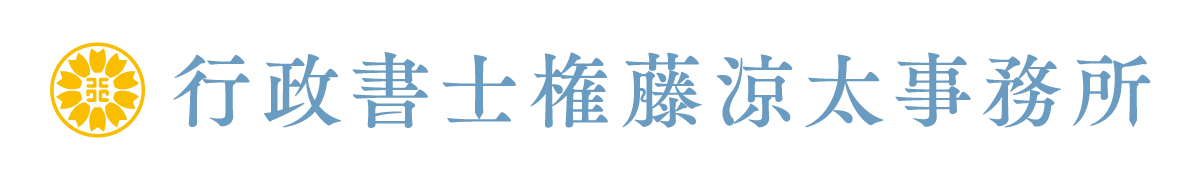











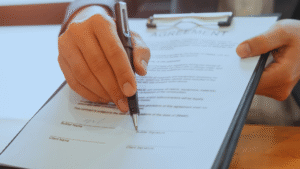
コメント