はじめに
お店を経営していると、思いがけずネット上で悪質な書き込みをされたり、身に覚えのない誹謗中傷を受けたりすることがあります。Googleレビュー、X(旧Twitter)、Instagram、口コミサイトなど、誰もが自由に意見を発信できる今、ネット上のトラブルは他人事ではありません。
では、もしあなたのお店がネットで中傷されたり、虚偽の投稿が広まってしまったらどうすればよいのでしょうか?
この記事では、被害を受けたときの具体的な対応手順と、行政書士にできること・できないことを、法令に基づいてわかりやすく整理します。
よくあるネットトラブルの事例
- SNSや口コミサイトに虚偽の投稿をされる
- Googleマップに「二度と行かない」「最悪の店」などの悪質レビュー
- 店主の顔写真やプライベート情報を晒される(晒し行為)
- 偽のアカウントで自店を騙るなりすまし被害
- 商品画像や文章を勝手に使われている(著作権侵害)
まず何をすべき?ネット誹謗中傷への初期対応
- 感情的に反応しないこと(反論投稿は逆効果になることも)
- 証拠を保存(スクリーンショット、URL、投稿時間、発信者IDなど)
- サービス運営者に削除申請や通報を行う
- 投稿が名誉毀損や業務妨害に該当するか確認
- 必要に応じて弁護士など専門家へ相談
ネット中傷はどんな罪になる?法律での位置づけについて
以下のように、民事・刑事どちらにも発展しうる行為です。
| 種類 | 該当する行為 | 主な法令 | 担当窓口 |
|---|---|---|---|
| 民事 | 名誉毀損、プライバシー侵害、信用毀損、損害賠償請求 | 民法第709条、不法行為責任など | 弁護士/本人 |
| 刑事 | 名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪、脅迫罪 | 刑法230条、233条等 | 警察/検察 |
| 行政 | サイト運営元への削除依頼、プロバイダへの情報開示請求 | プロバイダ責任制限法(改正あり) | 総務省・各事業者 |
行政書士にできること、できないことを正しく知る
行政書士に「できること」
行政書士は弁護士のように代理人として交渉や訴訟はできませんが、トラブルの整理と予防の側面で、次のような支援が可能です。
1. 事実関係・証拠の整理支援
- 被害内容の時系列整理
- スクリーンショットや投稿ログの保全アドバイス
- 状況整理シートの作成支援(弁護士相談時にも役立ちます)
2. 削除申請文書の文案作成
- サイト運営者宛の削除依頼文の文案作成
- 削除依頼に添付する経緯書、被害報告書の作成 ※削除申請は本人名義で提出する必要があります
3. 内容証明郵便の作成支援(非請求型)
- 投稿の削除を求める冷静な通知文(警告文として)
- 相手方に「被害を受けている」という意思表示をする手段として
注意:金銭請求や損害賠償を含む内容証明は弁護士の領域です。
4. 利用規約・プライバシーポリシーの整備支援
- 自社サイトやSNSでのガイドライン策定
- 無断転載や荒らし対策としての「利用上の注意」の明記 →【予防法務】として非常に有効
行政書士に「できないこと」
以下の行為は、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)により、行政書士が行ってはいけません。
| 禁止されている行為 | 説明 |
|---|---|
| 相手との交渉 | 投稿者と直接交渉・やり取りを代行すること |
| 損害賠償請求の代筆 | 「〇万円払え」などの法的請求文の作成 |
| 裁判や訴訟の代理 | 弁護士にしかできない |
こんな方に行政書士のサポートが有効です
- 「裁判まではしたくないけど、誹謗中傷は止めたい」
- 「どう対応してよいか分からない。まずは整理したい」
- 「弁護士に頼むほどの案件かどうか見極めたい」
- 「自社のホームページにトラブル対策を盛り込みたい」
まとめ|ネットトラブルは”初動対応”と”予防策”がカギ
ネットでの誹謗中傷や風評被害は、事業者にとって非常に深刻な問題ですが、
初動対応と法的整理を正しく行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。
行政書士は、訴訟や請求を行うことはできませんが、
「泣き寝入りせず、冷静に備える」ための伴走者としてお手伝いが可能です。
【参考法令】行政書士法第1条の2、第1条の3(業務の範囲)弁護士法第72条(非弁行為の禁止)プロバイダ責任制限法、刑法第230条(名誉毀損罪)民法第709条(不法行為による損害賠償)
ご相談について
当事務所では、店舗やネット事業に関するトラブル防止・文書対応支援を行っております。
まずはお気軽にご相談ください。あなたのお店やブランドを守るために、一緒に考えましょう。
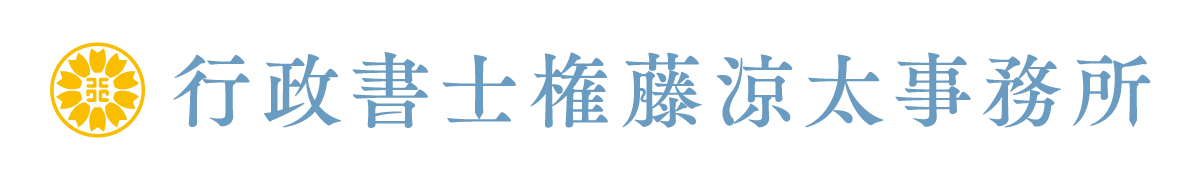







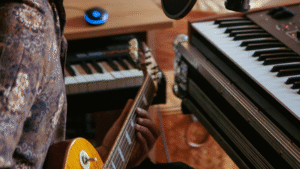
コメント