~音楽・SNS・創作活動を守るためにできること~
こんにちは。福岡県久留米市の行政書士、権藤涼太です。
このたび、日本行政書士会連合会が実施する「著作権相談員 養成研修」を修了し、所定のテストにも無事合格いたしました。
著作権相談員とは、著作権に関する基本的な相談に応じられる行政書士として、登録制度や権利関係、契約などの相談対応力を高めることを目的とした制度です。
研修では著作権法の基礎から登録制度、実務上の留意点まで幅広く学び、クリエイターや事業者の方々に寄り添ったアドバイスができるようになることを目指します。
◆ 実は“自分ごと”だった著作権の話
私自身、若い頃から音楽に関わってきました。少し前の話ですがDTM(デスクトップミュージック)を使った作曲活動や、YouTubeなどへの投稿を通じて、自分の作品を発信したこともありました。
そんな活動の中で、実際に「これは著作権と深く関わるテーマだ」と感じる場面がいくつもあったわけです。
アマチュアであっても、盗作や無許可での使用、アイデアの模倣といった問題は身近に存在しており、クリエイターの悩みや不安を“他人事”とは思えません。
だからこそ、「創作物を守るにはどうしたらいいか」「何かあったときにどう備えておけばいいか」という視点が、より強く意識されるようになったのです。
◆ 著作権とは? 創作した瞬間に発生する“無形の財産”
著作権とは、自分が創作した作品を法律で守る権利のこと。
音楽、絵、文章、写真、映像、デザインなど、「表現」されたものであれば、その多くが著作物として保護されます。
そして著作権は、誰かに申請をしなくても、自動的に発生します。
つまり、「登録しないと権利がない」というのは誤解です。
◆ それでも“著作権登録”が必要な理由
ではなぜ著作権登録という制度があるのか?
その理由は、いざという時に「自分が先に作った」ことを証明する手段になるからです。
たとえば…
- 作品を企業に提案した後、類似のデザインが商品化されていた
- 作曲した楽曲を他人が「自作」として発表していた
- オリジナルキャラクターが無断で使用されていた
こうしたトラブルの際、文化庁での著作権登録制度(登録原簿への記載)が、公的な証拠となることがあります。
登録には要件や手続きがありますが、「証拠を残したい」「後で揉めたくない」というクリエイターにとっては、安心を担保する“保険”のような存在とも言えるでしょう。
◆ 著作権の対象はこんなにも身近
「私はプロじゃないから関係ない」と思っていませんか?
実は、次のような活動も著作権の対象になる可能性があります。
- DTMやギター演奏によるオリジナル楽曲
- SNSで連載しているエッセイや4コマ漫画
- ブログ記事、ノウハウ資料、セミナー資料
- YouTubeで公開した動画、トーク内容
- 自作LINEスタンプやイラスト作品 など
そして最近では、AI生成物の扱いや、ゲーム実況、切り抜き動画など、判断が難しいグレーな領域も増えています。文化庁ならびに有識者会議でも様々な議論が行われているようです。
行政書士としての私にできること
今回の研修で得た知識を、今後の実務に活かしながら、以下のようなご相談に対応してまいります。
- 著作権登録制度(文化庁)に関するご相談
- 契約書における著作権の取り扱い(譲渡・利用許諾など)
- トラブル防止のための記録や証拠の残し方
- SNS発信やYouTube活動に関わる権利の注意点
- 自作作品の販売・公開時の注意点 など
行政書士として、契約や届出の手続き面からも支援できるのが、他の専門家との違いです。
「創る人」の味方として、丁寧なサポートを心がけています。
創作の裏には、守る手段がある
創作することは、誰かの心を動かす素晴らしい営みです。
その思いが、知らない誰かに無断で使われたり、価値を奪われたりしないように。
「守る手段を知ること」も、クリエイターとしての大切な力です。
著作権登録やご相談はお気軽にどうぞ
- 「この作品、登録すべき?」
- 「契約書に“著作権は譲渡しない”って書くにはどうすれば?」
- 「SNSの投稿、どこまでが著作権?」
そんなお悩みに、わかりやすく対応いたします。
お気軽にご相談ください。
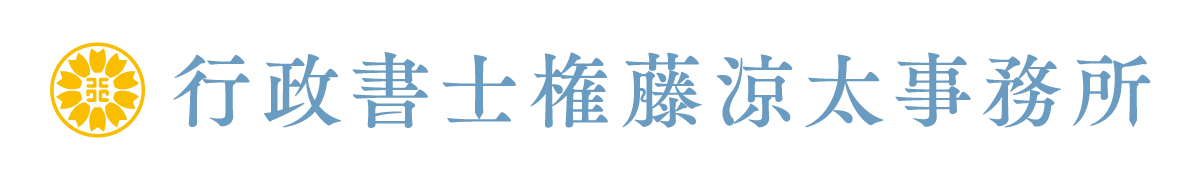








コメント